五十四 弾正台へ出願
弾正台とは各藩の悪い政治を聞き人民が訴える方法のないものため或いは旧来訴えても一向に取り
上げにならなかったり、公明正大にしなければなければならない役人が判断を間違ったりして涙を飲
んで汚名を着る場合に用いられます。また、とどのつまり直訴をすれば違法無礼として極刑に処せら
れ一族一門も連座処刑されるので余程でなければ直訴は殆どしませんでした。
ところが、王政維新ともに復古してこの弾正台も再興された各諸藩の領内に置いて訴える途のない
哀れな人民のために巡回する検事局のような組織で順繰り各地を廻っていました。その台長は玉野候
で心が清くて私欲のない人で誠に人に接するのに親切であるというその当時としてはめずらしく良い
役人という評判のいい方でした。その方が高崎付近の民情視察という任務を受けて高崎の大信寺を仮
舎として滞在しておられました。この事件の眼目から言えば打って付けと言わねばなりません。とこ
ろが藩でもなかなか用意周到で充分に見張りを付けて近づくようにさせなかったのは容易に訴えるよ
うにさせないためでありました。このように藩で怖れたのは東山道鎮撫総督の宮に直属しご布告に基
づき人民の困難状態や隠れて訴える途のないえん罪に苦しみご皇恩に浴することのない者や且つ領主
と領民の間にわだかまりのある騒ぎなどに何くれと聞きただして恵みを施してくれるからであります。
どんな方法かというとその出張所の門前の見やすい場所に投書箱のような物を置きその傍らに掲示
してもし訴願しようとするものがあれば要件が大体分かれば別段姓名等記さなくても構わないという
風に示されていました。それは訴願が容易に簡便にできるようにしたからです。そして投入の願書の
中から検討すべきものかどうか選択していちいち公明正大な処置を執られました。ちょうどこの減納
問題にはおあつらえ向きですが百姓は毎日町へ行きどうかして近づき願書を投げ入れたいと思っても
できないのは藩の監視が厳しかったからです。余り長くない滞在日も何日とはなく過ぎいよいよ役人
も明日当地を引き払うという風説が流れました。これを聞いた農民の落胆は大変なものでしたがこれ
も遺憾ともしようのないものでした。
ところで本訴願に関係した六十一カ村の内、最も熱心であった下中居、上中居両村の百姓代吉井宮
三郎、吉井久次郎、清水元吉、角田庄左衛門、松本佐五右衛門、清水徳次郎、丸茂小文吾、堤和三郎、
堤清左衛門、設楽富太郎、嶋田長兵衛、佐藤玉五郎、木村主馬吉、木村文四郎、佐藤代次郎、佐藤忠
兵衛、高尾弥惣次(佐藤三喜蔵は処刑、丸茂元次郎は上京中)の面々が協議をしたが大体の意見は道
中人目の少ないところで差し出すより外にないということになりました。従って多人数では仕損じが
あるから機敏で度量のある者といことで人選しましたが、結局吉井宮三郎、吉井久次郎の両氏に決ま
ったのはもう夜更けのことでありました。
両人はかねてしたためてあった願書を受け取り、一同に暇を告げて家へ帰り急きょ仕度をして三番
鶏の鳴くのを合図として出発しました。そのその扮装は常に伝馬人足に行くときのように竹の力杖に
風呂敷に弁当を包み手軽な服装でどう見ても訴願人とは思えませんでした。両人はまず倉賀野宿をで
てそれとはなく様子を窺ったがまだ弾正台の役人はまだ通 らないようであると両人は思いました。こ
こは高崎領分で危険この上ないので岩鼻目指し歩きました。さてこうなっては誰も同じ様なことを考
えるもので、下佐野の総代に堀口久四郎という深い考えのある方がいて結局弾正台役人が引き払うの
を幸いと自分が書いた願書を一層入念に清書しその夜のうちに有能な三人の仲間と相談し手筈を調え
上佐野の関口源七をこの役に選び出発させました。中山道を東京へ駕篭で行くのだから途中一、二泊
はするだろうとその時を見計らって差し出そうという考えでありました。この人はよく伝馬人足に出
て道中の様子をよく知っているので願書は懐にしっかりとしまい家を出ました。午前六時頃倉賀野あ
たりで前方で二人の通行人が後ろを時々振り返るのでよく見ると平素懇意のある上中居村の久次郎と
宮三郎の両人でありました。これはとばかり顔を見合わせたが奇妙なのはお互いに力杖と風呂敷をも
っていて旅人でなく伝馬人足という感じでありました。この時言うに言われぬ感慨がお互いに込み上
がってきました。そこで近くの路傍の石に腰掛け願いが同じなのでいろいろ相談をし、相方とも協力
して成し遂げようということになりました。
それから三人連れ立って歩いて行きますと遥か彼方に幾挺となくかごの来るようなので、きっと弾
正台の役人の一行であると心中喜んで歩いていると案の定その役人の一行であることが分かりました。
三人は直ちに願書を提出しようとも思いましたが高崎藩の家中も付き添っているかも知れないと思い
その後を追いていくことにしました。そうすると一行は宿で休憩し、人足を差し替えて深谷の宿目指
して出発し、高崎藩の役人も引き返すようなので久次郎、宮三郎、源七の三人は小躍りして喜びまし
た。まもなく役人は出発したので前後左右気を配って後をついて行くと日もはや暮れる頃一行は宿に
泊まる様子でありました。三人は宿に泊まるので願書を渡すのはさほど難事ではないと思い宿屋の主
人に依頼して取り次いで貰うことにしました。夕飯の住む頃合いを見て主人に会い折り入って頼んだ
が、この宿屋の主人は義侠心に富んだ方快く引き受けてくれました。そこで主人が役人のところへ行
き、その話を細かくすると役人の方も同情をもって聞き取り、三人に会ってくれることになりました。
宿屋の主人も心中どうなるか心配してい たのでほっとして宮三郎等三人を伴い弾正台の役人の居る部
屋へ行きました。三人の者は覚悟の上のこととし別段怖れた様子もなく厳かに懐から例の願書を取り
出して差しだし恐縮していると、役人は早速その願書を読んで非常に驚かれた様子でありました。文
面は率直な書きぶりでその概略は、
「居屋敷畑等は永納にしてもらい、また田方もこれまでの五割五分増しでは百姓が一層難渋を感ずる
ので元取りにして貰い、それができない場合にはせめて新領並にしてほしい。新領の取り立て方は元
取りの外一割五分増しで四割の違いがあり均一平等に取り立ててほしい。」
という内容でありました。役人は他の宿屋にも分宿しているので相談してから返事をくれるというこ
とになりました。そして役人は台長玉野候と相談をし玉野候は三人の者をその席に呼び入れ先ず願書
をお返しになりました。それから三人は代わるがわる事情を細かく話すと台長は高崎で箱訴できず私
達をここまで追ってきたことに憐れみ、同情を寄せてくれ話してくれることには
「よく聞け、直訴をする者は直ちに召し捕る掟であるがそうすれば一同の百姓が難渋するであろう。
同情すべき所もあるので格別の取り扱いをし、高崎で箱訴したものと取り扱い、特別に赦免するが万
一高崎藩の者がこの宿に来て逮捕されるようなことがあると大変だから、もっと安全な宿を紹介する
から安心しなさい。」
ということで三人はほっと一安心し、台長玉野候のご慈悲を感謝し、心からお礼を言いほかの宿へ移
りました。三人は昨夜以来の心痛を幾分慰めることが出来たので幸せといわなければならない、あま
りのうれしさにろくろく眠ることができないほどでした。翌朝早く宿を出て故郷まで八里(約三十キ
ロメートル)の道を昼前に着くように迅速に歩き無事自分の村に着くことができました。そして堀口
氏初め主な人達に細かにその次第を話しますと一同は非常に喜び三人の労を感謝し多大の効果を期待
したのは無理からぬことでした。しかし、後日別段、はっきりした効果は現れませんでしたが地租改
正上有力な資料となった言うことであります。そうすればこの行為は直接効果はなくても村民の利益
をなしたということができると思います。
五十五 大総代等の上京
高崎藩においても大勢の百姓が一旦入京しても漸く連れ戻しそれぞれ説諭を加えて帰村を許すとい
った至極穏やかな様子であるから時折、郡中を見回るくらいで監視もだいぶ緩くなってきました。そ
こを幸いと主な総代は密かに上京の仕度をし、丸茂氏は入京しているのでその後に続いて馬場安五郎、
小嶋喜伝次、岡田友右衛門、堤和三郎、小嶋掃部次、大澤富太郎、静野幾太郎、小平国太郎、高橋富
太郎、松田作平等の諸氏もつつがなく入京することができました。
一方丸茂氏は先発の山田勝衛氏の仮住まいを訪問し一別以来のことについて丸茂氏等から、一時国
元における物騒な状態、川越町まで来て取り押さえられたこと、今度は大勢で来ず主な総代だけが入
京したこと、新しい大総代に丸茂、福田両氏がなったこと、三喜蔵、喜三郎両氏の処刑、獄中にいる
文次郎の身の上などの一部始終をしました。山田氏は嘆声を発しながら、身を乗り出して聞いてまし
たが、
「第二の大総代も決まり、あなたのような意志の強い方がその任に当たり、双肩を負い今度のように
上京されたのは誠に喜ばしいことで、私達のできる限りの助力をしたい。」
と大いに同情をもって慰さめてくれたので丸茂氏も一層力強く思われ、尽きぬ話にその夜はそこに泊
まり翌日になり出願の手続きについていろいろ協議をしましたがこれから主な総代が入京するのでそ
れから十分協議をした方がよい、それについては用心堅固な宿屋が必要であるということになり山田
氏は
「私は上京して以来探しましたが確かな宿がありますので安心してください。一つは芝口一丁目の田
中屋忠左衛門といって主人は義侠心に富んだ方で少しも心配することはありません。また一つは新宿
の扇屋茂右衛門氏でこの人 もなかなかよく世話をしてくれる人である。」
と答えたので丸茂氏も大いに安心し
「新宿は川越よりの入り口で至極便利であるが高崎藩の監視もこの辺は厳重なので、芝の田中屋の方
がよいのではないか。」
と相談に及んだので山田氏ももっともな注意周到な言葉に同意し、直ちに田中屋へ宿泊することにし
ました。その日直ぐに山田氏の仮住まいを出て芝の田中屋へ向かいました。その途中高崎藩士に見つ
からないようにと気を配りながら田中屋へ行きました。そして主人に忠左衛門氏に面会し概略を説明
しましたところ、主人も大いに同情してくれ、細かい配慮をしてくれたので、両氏も力強く思い他の
総代の入京するのを待っていました。
その二、三日後に前に述べた十余人が田中屋の奥の倉座敷でいろいろ協議をしました。その結果、
丸茂元次郎、山田勝衛、静野幾太郎の三氏は常詰めで願の手がかりを求めること、その他の総代諸氏
を補助として二、三人残りそれも他の総代と代わるがわるつ勤める約束をし、その他の人々はひとま
ず帰り藩の動勢をうかがい、通信を怠らないように約束をしました。
話変わりまして別働隊の羽鳥文吉、久保田房吉の両氏も上京していて願の手続きを探し求めていた
が、良い手がかりもなくこれから先どうしようかと考えていました。
そんなある日浅草蔵前通りで偶然に甘楽郡一之宮の剣士山口藤十郎氏にめぐり会いました。山口氏
は両氏に向かい
「見受けるところ、東京見物に来たようにも見えず、何か心配事あるように見えたがどんなようがあ
って東京に来たのか。」
と尋ねたが両氏は躊躇して答えなかったので山口氏はこれには何か深いわけがあると思い
「ともかく、ここでは立ち話もできませんので。」
といって付近の茶店へ両氏を連れてきました。女給仕は愛嬌よく、茶菓や煙草盆等を運んでき、その
うち酒も肴も運ばれてきて世間話から今回の上京についてのことの次第を両氏が山口氏に詳しく話し
ました。
山口氏もこの話を聞いて両人が身を犠牲にして六十数ヵ村の百姓の難渋を救おうとするその義気に
感動して大いに同情を表してくれ、山口氏の旅宿の馬喰町の梅鉢屋治兵衛方へしばらく滞在しており
ました。そして山口氏は当時の太政官の大書記官服部一郎という方を紹介してくれました。そして服
部氏の尽力により民部省にするに訴願の手続きについて知ることができました。それより両氏は服部
氏をときどき訪問して願書の手続きを詳しく聞いたり、願書提出の指揮を願ったり等その苦心は大変
なものでした。
五十六 丸茂元次郎、東京で商人に変装
丸茂氏等五、六人の総代諸氏は知恵を絞り願書の起草に取りかかり、
半ば脱稿しようとしたとき、ある知人が
「高崎藩より岡っ引き等十人ばかり馬喰町辺に宿を取り日夜手分けし
て総代を捜索している。」
という知らせが入りました。丸茂氏はこれは容易でないと、宿の主人
の忠左衛門氏を座敷に呼びこのことを話すといったんは驚かれたよう
ですが、しばらく考えて
「それは皆様の心配は無理からぬことですが、しかし私も皆様より事
情を聞き、一旦引き受けたからには皆様にご迷惑をかけることは絶対
致しません。皆様が来てから二、三の者を派出させてその辺の見張り
をさせております。間違いのできるような不都合は致しません。どう
ぞ安心してください。」
と、真剣に言われたので居合わせた諸氏も大いに安心し、且ついつもながら忠右衛門の江戸っ子気質
の義侠心に感服し、一同より謝辞が述べられました。そこで宿の主人も一層総代の出入りに注意して
翌日より出入り口を裏に設け、見張り番を起き注意の上にも注意をしてくれたので何の不都合もあり
ませんでした。これは忠左衛門氏が義侠にでたのと、また一つには五万石領全般の塗炭の苦しみを救
おうと命をかけて減納訴願に苦労している総代諸氏に天が憐れんで岡っ引き等を近づけなかったのか、
何れしても一同は安心して市中を歩くことができました。
しかしまだ良い手がかりもなく毎日のように市中をあちこち歩いていましたがある夜、総代諸氏に
「私達訴願人を捕らえようと高崎藩より捕り手の役人も十人余りわざわざ東京へ派遣されて日夜捜索
しているから捕らわれるかも知れない。そこで私は商人に姿を変えて捕り手の者を欺く手段としてあ
ると思うが・・如何か。」
一同も
「それはよいと思う。でも最初はやはりごく手軽な子供相手のものはどうだろうか。例えばおもちゃ
屋などは一寸面白いと思うが・・・」
丸茂氏もそれに同意して、その手筈を田中屋の主人に頼むことになりました。主人の計らいで小さな
家を借りおもちゃの仕入れも一切田中屋が心配してくれたので忽ち一軒の玩具屋ができあがりました。
丸茂氏は玩具が売れようが売れまいがそんなことには頓着せず、毎日毎日もしや良い手がかりがない
かと商品を担いで出かけました。
五十七 丸茂元次郎の捕らわれの夢
元次郎氏は根気よく毎日天秤棒を肩に玩具の商いに出て世間の有様を見たり、良い手はないかと考
えたりして大道を歩いてましたが、どういうことかしきりに眠気が差し、眠く居眠くて仕方なく道ば
たに座り込んでうとうとしていると岡っ引き、別手等が幾人となく丸茂氏の身の辺りに来て前後左右
より取り囲み、元次郎神妙に縄にかかれと飛びかかってきた、今は逃げる途がなく無念の歯を食いし
ばり遂に捕らわれた、元次郎氏は三喜蔵氏に代わり第二の総代になり、艱難辛苦して漸く上京してま
だ願いの手続きさえなく、このように商人に扮装して苦心しているのに捕らわれるとは残念至極と思
わず、憤怒の声
「わぁーーーーーーー・・・・・・・・」
というその声が自分の耳に入りふと目が覚めてみますと東京の往来の真ん中で辺り近くには怪しいも
のは何もなく、全くの夢であったか、助かって良かったこれが夢でなかったら大変と心に思いつつ不
思議なこともあればあるものと心中やや穏やかでなかったので、商いは止めて直ぐに田中屋に戻りま
した。そしてそのことを一同に話すと
「実に不思議な夢だ。善か悪か何かの前兆だろう。」
という者もおり、それよりというものは一層に注意を厳重にして、不慮の災難に遭わないように警戒
をしたそうであります。
丸茂氏はどうにも不思議で耐えられなかったのでこのことを書面で故郷の父勘右衛門氏の許に知ら
せました。勘右衛門殿も親心より事なきを何より幸いとしたが、これは何かの加護よりこのような暗
示を得たかも知れないと日頃元次郎氏が信仰していた同村の稲荷の社へ参詣に行きました。そして別
当職の堤氏宅に寄り、
「せがれの元次郎が、このようなことを言って来たので、もしや神様の加護より遭うべき災難に遭わ
ず、夢に知らせを得たのだろうと思い、日頃せがれが信仰している稲荷様へお礼に参詣をした次第で
す。」
と一部始終を話しました。別当の堤氏は暫く勘右衛門氏の顔をじっと見つめていましたが
「これこそただごとではない。今あなたが話した令息元次郎氏が東京で召し捕らわれたというその夜
私は東京より元次郎氏が捕らわれたということを知らせに若者が来たかと思っていたら側に寝ていた
家人に起こされて初めて夢であったかと大いに安心したが、今あなたよりこのことを聞いてますます
不思議なこともあればあるものだ。」
と暫時不思議の感に打たれ話し合ったが、とにかくお稲荷様の守護もあったろうと共に神前へ燈明を
奉ろうと用意をして拝殿に上ったが拝殿の真ん中に新しい捕って縄みたいなものがあるのでよくよく
凝視しますと、ちょうど人が縛られ、縛られた者が縄を抜け出たようになっていましたので、大変驚
いて神慮の程を畏みて神前を下りました。この話を聞いた人々はますます奇異の感に触れ、人間の思
慮では考えることができないと皆々話し合ったということであります。
もっともこのような夢は不思議には相違ないが、古来の伝説には往々霊夢ということがあるがこの
夢はその夢なんでしょう。一概に夢は五蔵の疲れより来るものだとするのは卑近な一説で、宗教にか
かわらず哲学上より判断しても実際に不可思議なことがあって、諸事万端物質的な西洋人さえ迷想な
どという単純な考えは持っていません。いずれにしても、夢は確かに一種不可思議な霊妙を持ってい
る神妙な心的作用でございませんか。よって今、丸茂氏が見た夢もあながち軽率な評はできるもので
はありません。
五十八 稲荷に願書を頼む
人間の思索を絶し不可知的な領域より一道に接することは世間には例は乏しくはありませんが、歴
史上名高い宇佐八幡神託のようなものでしょう。そこの霊夢を聞きました人々の中でご神慮のほどを
知りたいという者がいて、中座に目隠しをさせまして大勢が祈りましたところ忽ちその稲荷が中座に
乗り移って、その口を借りて言うには、
「今や高崎様より別手数人捕り方引き連れて上京して馬喰町の武蔵屋に宿を取り日々諸処に元次郎を
召し捕らえるために捜索しいよいよ元次郎の居場所も分かり、召し取りの準備もでき、まさに召し捕
らえようとしたときに日頃我を信仰しているのでヤピッコを遣い元次郎の身代わりにたたせ捕縛され
たままここまできて、神殿において縄抜けをさせた。」
とはっきり述べたので一同の面々も神意の程を畏れて互いに顔を見合わせるばかりであったが、中座
は再び口を開き、
「知事公はこの減納願いのあることやこの騒動のことを家臣が知事様の耳に入れずに秘しているので
仕方ない。この上は直接知事様に願書を奉るより他に方法はない。」
というかと思うとそのままどかっと倒れました。聞きいっていた一同の者は東京における元次郎の身
については安心しましたが、減納訴願についてはこの趣を他の総代と相談をしました。そうすると、
これは奇異の現象であるからとにかく願書を藩知事へ差し出そうと決め、これを稲荷様に託して藩主
へ直接提出しようとしました。その願書の文面は、
お恐れながら書き付けを持って嘆願書を提出いたします
当藩支配所上州群馬郡五郷六十一カ村の百姓総代として下中居村百姓三喜蔵外二人が申し上げます。
私共村々は先主安藤対馬守様からの引き続きの仕法で知事様においては難しいとは思いますがここ数
年村々の者は実に困窮し詰め至極難渋しております。王政一新になり下民の願いの筋あれば願い出よ
との布告がありました。仰せでもありこれまでの取り立てではとても上納が難しいと右三人のものが
総代になって畑方永納、田方年貢延口米その他の品々の取り扱いのこと、ご定免願い、再度嘆願申し
上げましたが採用していただけませんでした。他県同様畑方永納、田方延口米について下民の願い通
り本三五村同様にしていただけると大変ありがたいと思います。
次に昨年十一月、総代三人の内三喜蔵、外七名召し捕らわれお屋敷へ引き立てられ入牢されてしま
いました。右村々の百姓が驚きましたがご処置もなく、本年二月四日抜き打ち斬罪となり、全老若男
女子供に至るまで昼夜寝食を忘れ悲嘆に迫り、追々処置があると一同謹慎していましたが長い間処置
がありません、何とぞご慈悲、憐れみの沙汰をお願いいたします。今存命の文次郎へ永年の沙汰お願
いします。仰せ聞いていただければどのような処置となりましても後悔いたしません。昨年の上納の
通り永く嘆願の村々が序の右できますようお願いいたします。三喜蔵、喜三郎に対し一年の御用捨て
右両人並びに永牢者へ約定たたずとも百姓謹慎しおりますので恵みのある、憐れみのあるお沙汰をお
願い申しあげます 以上
明治三年
上州群馬郡五郷 村惣百姓
上中居村 神方
高崎藩知事様
このような長々しい願書でありました。これも不思議のひとつですが、この願書を中座に渡しきち
んと懐中にいれてさっと立ちますと願書は当人の体に付着していません。前後幾十人もいてのことで
すから疑うところは少しもありません。実に不思議なことがあればあるものだと集まっていた人は感
嘆してたというが重ね重ねの不思議なことではありませんか。
五十九 本隊と別働隊との首領、神田明神で出会う
ここに東京にいる丸茂元次郎、山田勝弥、岡田友右衛門の三氏は民部省に強訴する事に決め、また
堤和三郎氏は地元に帰り協議したが、他の役所と違って民部省で願書を取り上げてくれたら、長年の
願望も成就する事疑いない、この上は三氏の身に恙ないように神仏にお願いするのがよいというので
皆それに従いました。
話が少し前後しますが一寸申し上げておきます。丸茂、山田、岡田の三人は意を決し、いよいよ近
い内に強訴に及ぶという二、三日前まず神社仏閣を礼拝し、天下の形勢はどんなものか、世間の有様
はどうであるか。維新の後太政官でも朝令暮改の訓示もあって、世は混沌としていつ太平の世の中に
なることかと人々の心も何かと落ち着かない様子である。三人が神田明神へ参詣して神前に願望が成
就するように祈念を凝らし振り向こうとするとき、不思議にもそこでばったりあった人はこれはなん
と減納訴願のため昨年入京した別働隊の東郷十二か村の総代でこの騒動の主唱者で諸事を放棄してこ
のことの成就のため東奔西走されている羽鳥権平、久保田房次郎の両氏でありました。しかし、世間
をはばかり辺りに一寸目を配り幸い他に人もいなかっので少しは安心し木陰に立ち寄り地元の様子や
当時の状況、世間の動勢までいろいろな話をしました。しかし、ここで逢うのも神の引き合わせたけ
れども、これから先どちらがどんなことに遭うかも知れないので、双方住所を明かさない方がいいだ
ろうということとなりました。
これが後に民部省に出頭したときにはなはだ不都合で連絡が双方になかったのは用心過ぎて却って
不用意のそしりがありました。このようなわけでであるから訴願の手続きについても親密な協議もで
きませんでした。勿論互いに世を忍ぶ身であるからのんびりと話し合うことができないのは無理から
ぬことではあります。そんなわけで充分な意思疎通をせずに両主領は東と南に分かれていきましたが
互いの胸中はどうだったでしょう。羽鳥等氏は馬喰町の宿舎にに帰り、今日幸い丸茂、岡田、山田氏
に思いがけず会うことができたが、事件についての様子は何分はっきり分からない、この人達も既に
民部省へ訴願したのだろうか、またはまだ手続き中であるか、それともなおまだ良い手がかりはない
かと心配しましたが、その後もいろいろな話が出てその夜は余り寝ることができませんでした。
翌日は二人揃って服部一郎氏の官邸を訪問し、それと話に岡田、山田、丸茂の三氏が訴願したかど
うかを聞いたが別にその様子もなく、また至急訴願せよとの指揮もありませんでした。ただ服部氏は
訴願の日時はこちらから通知すると言うだけでありました。そこで羽鳥、久保田の両氏は是非明日に
でも訴願したいからさせてくれとはとても言える状態でなかったからそのまま暇を告げて宿舎へ帰り
ました。
また一方岡田、丸茂、山田の三人は芝の宿を目指して歩いている途中羽鳥、久保田氏は訴願の手続
きはどこまで進んでいるのだろうか、もう既に訴願しているのだろうかなどとひそひそ話をして二人
を気遣っていました。その意中には自然強訴の競争を含んでいたと評する人もおりましたが、その辺
は皆さんの判断に任せることにしておきましょう
両首領は勿論、地元にいる者も岡っ引き等の目を忍んで食料の調達やら東京との信書往復等につい
て万事のかけ引き等苦心の程は想像の外でありましょう。
六十 丸茂、山田、岡田氏民部省へ訴願提出
岡田、山田、丸茂の三氏はそれまで長い間苦心されたがよい手づるもないだけでなく、高崎藩の方
でも厳重な捜索をしているので何時召し捕らわれるかも知れない、最早猶予はないと決心して前もっ
て書いておいた願書を懐中に入れ、民部省に出頭しました。直ちに願書を差し出しましたが、なかな
か沙汰がありません。だいぶ待って昼頃になる頃漸く呼び出しがありました。三人は、静粛な取り調
べであることを期待し厳格で神聖な白砂へ入りました。三氏は言うことのできない威厳に感慨無量で
あった。すると天司という役人が
「あなた達はこのような訴えをするのは至極心得違いばかりでなく、藩でも民情を掴み追々不公平の
ないように取り扱うからこの願書は却下する。よって故郷に帰りそれぞれの家業を励み安心して仕事
につきなさい。」
と懇々と説諭されたが、三人は天司の説諭ぐらい百も承知、空吹く風と吹き流していました。拝み倒
す主義でな頑固一点張りの主義を表現したので、役人はあくまで穏やかに話しているのに理解に乏し
いと不満の面もちで憤られてしまいました。結局三氏は白砂道心のため引きずり出されそうになった
のでその日はやむなく退廷しました。
三人は元より命を賭けて双肩を担った責任は、そんな一片の説諭位で引き下がっては女々しく故郷
に帰れましょうか、一旦退いた三氏は熟慮、協議して勇猛心を起こして、翌日明治三年八月七日再び
民部省に出頭して前日の願書を差し出ましした。今日はどういう風の吹き回しか小言も言われず控え
ていました。そうすると午後の三時頃白砂へ呼ばれ、しばらくすると荘重な語気で辺りを戒めるよう
な声がしてきました。天下の民部卿自身が見えたのである。三人は有り難くもあり、怖くもあり唾を
呑んで様子を見ていると卿殿は厳格な態度でいろいろ事件の発端から今までの有様や成り行きについ
て吟味されました。三人は臆せず怖れず百姓の難渋 の有様や凶作の状態、それに対する藩の処置等逐
一細かに説明をしました。卿殿は三人が余り熱心に話したので大いに呆れている様子であったが、突
然、
「お前達、そのように強訴するのでは仕方ない、入牢を申しつける。」
といって立ち上がり、そのまま奥に引き上げてしまいました。
ああ、何たることでしょう。そこで三人は役人に引き立てられ仮牢に収容されました。地元におい
ては各総代が代わる代わる東京との往復音信もしていたので東京の様子もよく分かり、いよいよ近い
内に民部省に訴願する手筈であるというので皆喜んでいたのに、その後何の便りもありませんでした。
今度はどうかしたのではないかと心配しているときに東京から帰ってきた堤和三郎氏は
「丸茂、岡田、山田の三氏は去る六日願書を民部省へ提出し一応吟味があって下がりました。翌日ま
たそこへ強訴に行ったので今度は入牢をいい渡たされた。」
と話され、三氏の様子が分かったので、福田子之七、小嶋喜伝次、馬場安五郎等その他主なる総代諸
氏は善後策について協議されました。その結果、ともかく入牢されている三氏の身の上や減納訴願の
許否を探知するためこれまで通り三、四人代わる代わる滞京する事に決まりました。このときの丸茂、
岡田、山田の三家の家族や親戚の人達の心痛の程は計り知れないものがあったでしょう。
当時強訴に及んだ者は一家断絶、親戚まで追放させられたそうであリますから、それなりの覚悟は
していたでしょう。しかし、かの芝居の桜宗五郎のように幼子まで刑場へ引き出されて悲惨の最後を
遂げなければならない運命に遭うものかと五万石領の百姓誰一人頭を痛めない者はいませんでした。
六十一 馬場安五郎等民部省へ召喚
堤和三郎氏が帰ってきての報告、三氏の強訴による入牢について主なる総代に連絡すると、すぐさ
ま三十人ばかりの者が忽ち集合しました。そして、その善後策を協議している席へ、上中居、和田多
中、上小塙村等の若者が汗を拭きつつ駆けつけ、
「馬場安五郎、堤和三郎、静野幾太郎の三人に、大至急高崎民政局へ出頭せよ、との通達ががあった。」
と名主から言われたので使者で来たというわけであると息も絶えだえ陳述しましたが、これを聞いて
いた諸氏は藩で三人のみを呼び出すというその真意が分からないのであれこれ心配するもののどうし
ようもない。三人はひとまず帰宅し、とにかく名主の家に行くと、名主も本人の出頭がなかったり、
逃亡でもしたら藩に申し訳が立たないので心配していたところなので、大変喜んでいました。そして
早速名主は三人を連れて藩の方に出向きました。明治三年八月十日呼び出しに応じた藩でも待ち構え
いた見え、係りの役人は
「ただ今より東京へ連行するので承知しなさい。」
と言いました。三人は呼び出されることさえ理由が分からないので東京へ護送されると言うことは全
く要領を得ない、罪人として護送するならば一応取り調べをして縄を掛けるのが掟であるから三人は
意を得ず戸惑っていました。しばらくすると民政使即ち旧米見役新井喜太郎氏が旅装してきて三人に
向かって
「ただ今より私が伴い東京へ護送するが道中心得違いをしないように、さあこちらへ来なさい。」
と言うのでいつてみると駕籠が四挺、それを担ぐ人夫が十六人何れもだいぶ待っていた様子であくび
などしていたが、この人足もやはり五万石領の百姓であったのでお互いに大いに驚きました。すぐさ
ま駕籠は八人の者にかきあげられ早駕籠のように昼夜続けて走りました。そして十二日の朝小石川の
館に着いたとき、付添人の新井喜太郎氏は早速元江戸家老の田中助之進殿へその旨を申し上げました。
一方馬場、堤、静野の三人は駕籠より降りると牢屋へ入れられると思ったが案外広い部屋で煙草盆
や茶菓子も出て、暫くすると朝食まで出てきたからこの先どうなるかと思っていたところへ新井氏が
再び臨席して
「ただ今より民部省の方へ行く。」
と、用意の駕籠に乗せられ、霞ヶ関の黒田候邸の民部省の白砂前で下ろされました。そこで新井氏が
退席し係りの役人へ引き渡されたがまだその理由が分かりませんでした。
しかし、三人は当省で調べられるのは願ってもない幸せとして、五万石領の百姓のために充分訴願
の意を伝えようと思っていたがなかなか取り調べが始まらない。あちこち白砂の模様などを見ていま
すと間口二十四間(約三十メートル)奥行き十間(約二十メートル)その内砂利間が十二間、三間と
いう壮大な建築はさすがであると心密かに驚嘆していました。その入り口の左右に椅子があり数人取
り調べを待つ者がいて、その内のある者が三人に馴れ馴れしく言葉をかけてきて、
「あなたがたはこの白砂へは初めての様子、どんな願いか分かりませんが、ここは普通の事件は取り
上げない、再三再四下がれ、の言葉がかかる、この場合どうしても取り上げて貰いたいと思ったら、
まずその前に自分の膝の前の砂利を掘り高く盛り上げ、いざとなったらその砂を役人目がけて投げか
けようとする気配を示せば役人もその決心のほどを酌量して願書を取り上げるがこの役所の一例であ
る。」
と細かに注意してくれました。その人は中国辺りの人である事件のために二年も経過したがまだ前途
不明であると話していたが、その内に呼び出され、取り調べの役人は厳格に着席されて、
「丸茂氏等の申し立ての証人とするばかなりでなく、民部省役人の中にこのことを一種の道具に遣い、
きっと聞き届けになるよう尽力したい。」
とまことしやかに説明して、金銭を巻き上げる好餌として農民を誘惑した事件について、民部大極殿
が仰るには
「当省役人吉野外記という者を知っているか。」
との尋問でした。これは先に民部省より派遣された役人で瀧之澤村の百姓を集めあるもの次第で訴願
に尽力するという話を聞いたことがあるかという調べでありました。馬場等三人は顔を見合わせ以心
伝心し、これはいろいろ事情があるようだと思いました。ついては
「以前、太政官の役人という触れ込みで吉野外記という者が『運動費として二百両も出せば必ず減納
願いを聞き届けるように尽力する』と言ったが各総代協議の上金銭は差し上げずご馳走を出して何と
ぞここ添えを願い『幸い貴殿の尽力で減納の願いが聞き届けになりましたら数千両のお礼をする』と
約束した。」
とも言えないから
「知らない。」と答えたのでこの日の取り調べは終わり退廷を命じられました。
白砂を出ますと高崎藩の役人もいないので芝の田中屋へ行くことになりました。宿へ着くと二、三
人の総代がいたので今度の東京での一部始終を話し、どうして民部省は瀧之澤村の件を知っているの
か、どうしてこのくらいのことで私達を呼びだしたのものかと顔を見合わせながら話しました。
それより地元のことやら、丸茂、山田、岡田の三人が一大活動をしたので年来の願いも成就するなど
との話をしたが馬場、静野、堤の三人が旅の疲れがあるから寝るように勧められたので総代諸氏の厚
意に従い床につきました。
さて、国元では馬場、静野、堤の三人が十日に名主に付き添われ民政局へ呼び出しになったまま名
主はその日のうちに帰りました。しかしながら、その三人は今日になっても帰宅を許されず、家人は
勿論主なる総代の心配も普通ではありません。入牢した様子も、郷宿へ預けられた様子もなく、何時
どんなわけで身に及ばぬこととなるか分からないなどと考えられたのも無理からぬことでしょう。
また田中屋に泊まっていた馬場等三人も地元で皆が心配しているからと十三日の正午暇を告げ旅路
につきましたが、今度の旅は狐にでもだまさられたようで一向張り合いもなく途も捗らず十四日の夕
刻漸く帰られました。それで早速他の総代諸氏にその旨告げましたのでその夜の内にに二十人あまり
が集まりました。そこで三人が遭ったことを細かく話したところ皆大いに喜んで初めて安心し各総代
もその労を癒し無事帰宅したのを大いに喜び、午前零時頃それぞれの家に帰られました。
六十二 丸茂、山田、岡田の三人民部省より高崎藩へ
そこで一旦借り牢へ収容させられましたが
「既にこの通り入牢させられたのはともかくも願いの筋は聞き入れてもらえると心中大いに喜び、何
時沙汰があるか。」
とひとえにその命令を指折り数えて待っていました。
民部省は小石川の邸へ通報をし、これを田中助之進は驚いて民部省へ出頭三人の引き取りを迫る、
漸く七日目の十三日に白砂へ呼び出されました。三人は心の中でいよいよ願いが叶えられるとワクワ
クして待っています。在京中の総代諸氏は今日民部省の控え室へ行き様子をうかがっています。
三条公等が着席になり厳かに、
「お前達より願いについてともかく検討してきたが、この度高崎藩より引き渡しの旨申し出があり、
当方もそれに応ずることにした。高崎藩によく言っておいたから強訴などせずご支配の世話になるよ
うに、おいおい政治の機構が変わり、日本国中総一体になるだろう。地元に帰って一般農民を慰める
ようにしなさい。この三年ぐらい慎んでいなさい。きっと安心するようになるだろう。」
と言ったので、三人は以外の申し渡しに憤怒の情を抑えることができず
「仰せはありがたかく思いますが、もし私共が高崎藩に引き渡されることになると、前総代の三喜蔵、
喜三郎らのように打ち首になります。一層当所において処分をお願いいたします。」
と嘆願に及び、列席の諸卿方も大変気の毒に思っている様子でしたが、高崎藩の役人も門前で待って
いる状態で諸卿もこの場に及んではどうすることもできず、前言を繰り返し退席してしまいました。
白砂の役人は三人を白砂外へ引き出そうとするが三人は動こうとせず役人も持て余し気味で呆れて
いましたが、これでは行けないと思い、強制的に三人の襟首を持って引きずろうとしましたが動こう
ともしません。三人は白砂の小石を掴み役人目がけて投げつけるような頑固な行動に出ましたが、三
人の考えはこうでありました。
「今ここで高崎藩へ引き渡されたら佐藤、高井両氏のように斬首の刑に処せられるよりもこの場でで
きる限りの防御をして、それでも引き渡されたら乱暴を働き、その罪の処分で高崎藩に引き渡される
ことはないだろう。」
と見苦しい振る舞いをしてしまいました。高崎藩より三人の引き取りのため出頭していた大参事田中
助之進は数十人の役人を従え民部省白砂の前で馬を下りました。白州へ入るや不始末最中で最初は大
いに憤怒したが、先ず引き渡しの手続きを終え、三人に対しても言葉を和らげ丁寧に懇々と説諭を加
えたので無事受け取ることができました。大参事の手腕もなかなかのものでした。白砂の役人も一時
は立腹していましたが、こう穏やかに引き渡しが済んでみると三人の行く末を心配して厚く世話をす
る様子が見受けられました。三人は用意された駕籠に乗り小石川の邸へ護送されました。昨年六月藩
主松平殿は高崎藩に任命されたので急に国元に帰られ、大勢の家来を連れて行ったので自然空き家が
たくさんありましたからそこへ三人を押し込め日夜厳重に警備をしました。しかし、呼び出しもせず、
といってひどい扱いもしないで幾日かが過ぎていきました。将来のことを考えこれまでの苦労が無駄
にならないようにと心に思っても今は入牢の身、せめてこのことを地元に知らせたいがそれもできな
い。こんな生活をしている内二十三日に呼 び出しがありましていよいよ三人は高崎へ転送される旨言
われ、途中二泊して二十五日高崎へ到着して入牢されたのであります。
六十三 大総代小嶋文次郎の処刑
ここに大総代の上小塙村の小嶋文次郎氏は昨年十月佐藤三喜蔵、高井喜三郎の両人が倉賀野宿の岡
っ引き三国屋のため召し捕らわれたので、この両人を救い出そうと義侠のため馬場安五郎、秋山孫四
郎、浦野嘉吉と共に岩鼻県庁へ駆け込み願いをしたが、両人を救うどころか、却って自分までも高崎
藩へ引き渡されました。今はそれから一年近く経ちその間牢獄に入れられてまま別段苛酷な取り扱い
もされず、また呼び出しになって取り調べも受けませんでした。ただその後、減納願いはどうなった
か、三人の大総代が捕らわれて、誰が大総代になったのだろうか、願いのことは続けているのだろう
か、三喜蔵、喜三郎の両人は斬首の刑に処されたのだろうかなどと様々なことを思い浮かべながらも、
我が身は囚われの身、この後どのようになっていくのだろうかと将来
を案じて、憂き月日を送っていました。
九月の菊の節句も間近い七日の朝のこといつもは同房の者はすべて
同時に食事を与えられるのに、今日に限って私だけ一人先に与えられ
るのはおかしいと思いながら食事に向かうと、いつもと違って山海の
珍味があり、皿に盛ってある魚の頭がなく、これがうわさに聞く打ち
首にされる日の朝食であるかと、感慨も一塩で顔色も青くなっていま
した。牢番の者は重役よりの命令であるから仕方なく小嶋氏に朝食を
済ますように慰めながら促しました。小嶋氏も余り突然なことだった
ので驚きもし 怒りもしましたが忽ち思い直されました。
私は五万石領百姓の難渋を救おうと決心しこの重圧に耐えている者
はどうして命を惜しむであろうか、大胆堅固の志士何の躊躇があろうか。そこで食事が済みますとは
や外には小嶋氏の乗る駕籠が用意してありました。
すぐ獄舎より引き出されて駕籠の中へ押し込められてしまうと駕籠は忽ち無縁堂へと担ぎ出され程
なく着くと付き添いの役人は小嶋氏を駕籠より出し新しい菰の上へ座わらせ
「今日、只今お前を処刑する。罪状を読み聞かすから慎んで聞け。」
と彼の三喜蔵、喜三郎両人の文面とほぼ同一なものを読み聞かせられた。これまでは小嶋氏も至極お
となしくしていたが今の罪状を憤然として役人をにらみつけました。
「私は命を惜しむ者ではない。元より覚悟の上で大勢の総代となって訴願している者、この場に及ん
で女々しい振る舞いはしないが、ただ今の罪状は聞き捨てならない。人を馬鹿にするのも程がある。
三喜蔵、喜三郎氏もここで毒手に触れ恨みながら果てたのだろう。」
とにわかに顔色が変わり、両眼に涙を浮かべ南無阿弥陀仏と何回か繰り返して、佐藤、高井両氏の霊
を伏し拝みました。この有様を見ておりました者は誰彼の別がなく、係りの役人まてが鼻をかむよう
な姿勢で暗に涙を払いつつ熟視されていた。
なんと悲惨な光景だろう!! 小嶋氏も最早逃れる術はないと覚り辞世をを詠じました。
身を捨ててよのためになむあれかしと祈る心の外なかりけり
そこで役人に向かい
「私は決してあなた方を恨まない。ただこの処置を執った者に対しての恨みは天が必ず晴らしてくれ
るだろう。早く処分をせよ。」
と厳然として首を差し出す、役人側も涙で袖を濡らさぬ者はいない、これも役柄、今さら躊躇する場
合でなければ小嶋氏の決心の一言を合図に牢番は刀を振り上げた。見る間に無惨な姿になってしまっ
た。
今度の処分は突然だったのでだれも知る者はなかったが数時を経て追々知れ渡り、まだ役人が無縁
堂を引き取らない内小嶋氏の親戚や村役人も駆けつけ役人に願って貰い下げ、泣く、嘆くのその悲哀
の光景をとても充分言い表すことができませんので推察の程をお願いいたします。小嶋氏の死体は仏
式をもって埋葬されましたが、これに会葬された者は親戚縁者の外五万石領内百姓代等未だかってな
いほどの盛挙でございました。
六十四 別動隊の羽鳥、久保田氏民部省へ出頭
ここに東郷大総代羽鳥権平、久保田房次郎の両氏は時期の熟するのを待ち、国元では各郷へ自分た
ちの考え方を浸透させ、上京中の諸氏には東西相呼応という策を用い、上京以来の苦心は本隊諸氏が
なされた困難にも劣らないほどでありましたが、それが余り人々の耳に触れなかったのは、即ちその
名称のように別働隊なので正面より過激に当たらないからであります。
丸茂、山田両氏が民部省へ強訴をなし、遂に高崎藩に引き渡された今日となっては最早これまでの
応援ではだけでは済まなくなってきましたので、両氏はどんな方法をもって事に当たるべきかについ
て協議をしました。その結果、この上は民部省へ訴え出ようと言うことになり早速民部省へ出向いた。
出頭手続きのため九月二十日の午前九時頃羽鳥、久保田の名刺を差し出し暫く待っていると呼び出し
になりました。見回してみると厳格な役所のことで思わず崇敬の念を深くしました。正面には民部の
大輔玉野東平殿の着座があり陪席の四名が並び例の通り尋問が開始されました。その概要は次の通り
であります。
問 住所氏名職業を述べよ。
答 私は上州群馬郡高崎藩士支配所東郷宿大類村農にして弘化四年五月生で本年二十三才、羽
鳥権平と申します。
問 次の者も述べよ。
答 私もやはり同郡同村同支配所同村農にて弘化元年八月生当年二十六才久保田房次郎と申し
ます。
問 出頭の趣旨を述べよ
答 私共の領主の上納取り立て法は昔から込め四斗二升入りを一俵として、金十両に付き四十
四俵替えのとき田、畑、屋敷共米納に定められていて、万一不作の年はご検見を願い、田の
坪刈りをして一坪の籾が一升ある時は玄米七合三勺あるものと見なし上納しなければなりま
せん。田の方は上納できても、畑や屋敷分の上納米がなく、そのため追々貧困の度も加わり
他領へ移転するものさえでき、食うに食えなく餓死する者さえいるような状態であります。
明治二年は近来稀な大凶作で規定の年貢を上納すれば家で食べる米は一粒もなく途方にく
れていましたが、今般王政復古のご維新となり万民の塗炭の苦しみを救うという趣旨の告示
もあり、私達総代はこのような状態を見るに忍びず、昨年九月訴願いたしました。それによ
り、大総代二名は斬罪になりましたが、昨年度一年に限り、高崎藩知事様が減納を聞き入れ
ていただきました。しかし本年は減納についての話はありません。
私共は他領を調べて見ましたが畑一反歩の上納金は永二百五十文で現金に引き直すと畑一反歩の
年貢金は一分くらいで、それが高崎領地では畑一反歩上納米四斗四升余りに当たりで このよう
な不均一な徴収方法は他には見られません。また上納米についても米見役人が各村を巡回して上
納米を取り立てますが、どんな良米を差し出してもその役人に饗応をしなければ何回も精選させ
ひどいときは十回以上もさせられて漸く納入ということになります。また不良の米でもある
ものの軽重により同格に納入されることもあって、農民がますます難渋が加わってきています。
これについて減納のお願いをしましたところ、藩政を罵倒しお上を欺くことと捉えている
向きがありますが決してそのようなことはありません。また目下私共は減納訴願の協議中で
すが評議の場所は榛名山の麓で集合の人数は五千人ばかりで話し合っております。こう申し
ては至極不穏の状況に聞こえるかも知れませんが高崎藩においては減納についての集合をあ
くまで阻害し、万一出願運動をするようなことがあれば片っ端から捕えられ入牢させられて
しまうので前述の場所を選んだわけです。
何とぞ寛大な処置をもって、他領同様畑、屋敷の分は永納で、田は七合三勺の摺り立て法を
更正して、他領同様の上納ということになりますよう嘆願する次第であります。
と申し上げると、玉野東平殿は
「あなた方の申し立ては一応もっともではあるが、古来より施行されている方法をこの席で改廃す
るということはできない。というのは数百年前の検地そのままであるから一反歩といっても実際一反
五畝あるものもあれば反対に八畝ぐらいしかないものもある。ただ今太政官では北は北海道から南は
琉球の果てまで同時に測量をし、田畑の称を止めてすべて耕地として、租税は金納とほぼ決定してい
る。着々不均衡を是正していく方針である。
今私はあなた方に対し、一時逃れの説諭をしているのではない。藩制度を廃止し真の王政復古をな
し天下の皇土でなければ、地の果ての皇臣でなければならない。このことを心に留めてておき、速や
かに地元に帰り農業に励みなさい。今より測量しても国中の測量が終わるのは五、六年もかかるだろ
う。その後は日本国中同一の法の下で均一の税法によって徴収されるようになる。それまでは辛抱し
て朝廷の仁政を待つ外はない。天皇の恵みが一般化の傾向もあり、漸次良い方向に是正しつつあるの
で強いて訴願する必要はない。これからすべて平等になるのでくれぐれも家業に励むように、あなた
達も農民に説明をしてほしい。私はあなた達を欺かない。速やかに国元に帰り従順に家業に励みなさ
い。」
と大変親切な説諭に思わず涙の出るのをきんずることができませんでした。こうまで懇切に、理路整
然と説諭されてはいかに頑固な連中でも、今玉野大輔殿の節を聞いては耳をかさずにはいられない。
とうとう両人は退廷して時機を待つことにしました。
こうなったからにはもう東京にいる必要はありません。早速荷物をまとめ宿の支払いを済ませ、世
話になった山口藤十郎先生に今回の事柄を話し、礼を言い暇を告げました。十月二十一日出発を氏、
二十二日新町宿本陣久保五左衛門方に泊まり、使いを日頃援助して貰っている某氏方へ出し、各村総
代のもとへも知らせました。そこに多数の者が集まりましたので、両氏の民部省への出頭の顛末や係
官の懇切な説諭などについて話し、
「太政官書記官の服部氏の話の内容が合致しているので、この上運動しても効果は余りないので、今
度の運動はここで一区切りをして、一時世間の動勢をうかがって時機到来を待ち、他日我々の村々だ
け更正されないときは命に賭けても聞き入れて貰うように尽力したい。」
と誓ったので一同の者も大いに賛同して安心し新町宿を出て帰村しました。それからは今までのよう
に訴願のことで東奔西走することなく、農業に励みましたので、他郷総代のように後に捕らわれるこ
ともなく安穏に過ごすことができたのは先見の明があったと言っていいでしょう。
六十五 一県二藩の役人評定
百姓側においてはこの春以来非常な手段をもって、弾正台や民部省、岩鼻県へ訴願したにもかかわ
らず、今年もはや稲刈りの季節となりこのまま過ぎれば全部の年貢を取り立てられるのは確実であり
ます。また大総代三人とも打ち首の刑に処され、それだけでなく民部省へ強訴した元次郎、勝弥の両
人も遂に高崎へ引き渡された様子なのでこの人達の身の上もどうなるかも心配になってきました。そ
こで福田子之七氏初め主なる総代は数回協議の結果いよいよ大勢の者を榛名山の麓蛇塚へ再び集合さ
せることに決定しました。このことを各村の総代に通知すると各総代はその手順は慣れているので迅
速に藩に気付かれないよう密かに連絡しましたので、四千五百人が一定の場所に集まるまで取り押さ
えると言うことはありませんでした。
そこで、大勢の者は蛇塚富士見カ原といって富士山も見えるのでこの名前がつけられたのですが、
夜は柏木沢村の東明屋や西明屋、生原村その他の近傍の村々に前もって総代等が借りておいてくれた
家々に着きました。このように大勢の者が泊まるので誰一人夜具や布団を伴って寝た者はいないくら
いで着のみ気ままで露営に等しき夜を明かしました。このようなわけでありましたから家を貸してく
れた人も大いに迷惑を蒙ったわけでありますが、苦情らしきことを言った者は一人もいませんでした。
却って厚く同情してくれ、各家あり合わせの芋、ごぼう、大根などをたくさん煮てくれたのには全く
頭が下がります。
朝の食事が済みますとまた富士見カ原蛇塚へ集合するということを繰り返していました。それはど
うしてかというと総代の考え方が異なり各藩に訴願する方が得策する者や高崎城下へ押し寄せるのを
支持する者などいてなかなか考え方が統一できなかったからであります。
数千の百姓が榛名麓蛇塚へ数日前より集合し、まだ解散の様子がないので一番憂慮したのは高崎藩
で、先に城下まで押し寄せられたり、そればかりでなく民部省へ訴願の目的をもって大勢の百姓が上
京したりしたので、今後はどう対処したらいいか重役は民政局へ詰めっきりで協議をしてました。百
姓が集合しているところが他領内であるから領主に無断で踏み込み解散を命ずるわけに行きません。
しかし、このままにしておけば民政省に対しても近藩、隣県に対しても面目が立たないが協議がまと
まりませんでした。この騒動が岩鼻県、前橋藩へ知れたのは先ず前橋藩で、高崎藩領内数千人が今榛
名麓で集まり何かことを起こそうとしている。隣藩なので黙ってはいられません。早速、重役会議を
開き
「岩鼻県は最初より関係あるからともかく岩鼻県と交渉し、その意見を聞いてから処置をしよう。」
ということになり書記官の児玉氏を岩鼻県へ使者として派遣しました。岩鼻県においてはこの騒動に
ついては藩と百姓双方の事情をよく知っているのが単独では仲裁できず、といって放棄しておいては
隣藩に対して申し訳ないと心配していたところへ前橋藩から使者が来たのです。
「高橋藩の百姓騒動については自分の藩ではこのような対処をしていますが貴県においては最初より
配慮されているので是非ご意見をお聞かせ願いたい。」
と言いますと県の書記官松本氏はこれまでの一部始終を述べ、今般のことについていろいろ話してか
ら貴藩と共に高崎藩に交渉して仲裁の労を執ろうと約束をしました。
そこで松本氏は中座してその顛末を知事に話すと知事も大いに喜ばれて高崎藩の交渉も松本氏に命
じました。松本氏は再び児玉氏に面会し、知事も貴藩の誠意を感謝しており、私が貴藩ともに交渉す
るように命令されたのでよろしく頼むと述べたので児玉氏も大いに喜ばれました。
ということで、松本、児玉の両書記官は急ぎ駕籠の用意をし高崎城内へ民政局へ乗り込みました。
同局には大参事長坂六郎氏外重役の方々が善後策についての会議をしている真っ最中でありました。
そこで児玉、松本両氏の来意を述べましたので高崎藩側でも両藩県知事の厚意を感謝し、両氏を応接
室に通し礼を尽くし茶菓など呈して至りつくせりでありました。この使者の両氏に対する人選は話し
合いの結果大官金子節右衛門氏に決まり、金田氏は両氏と協議したが、ともかく箕輪へ出張して百姓
を解散することにしました。
「しかし、今日は既に日も暮れてしまっているので、明朝早く箕輪へ出張する。」
と約束して両氏は暇を告げ宿の方に向かいました。
翌日明治三年十月八日で高崎藩よりは大目付の白井喜平、長坂只正の両氏、一県二藩の役人は箕輪
村目指して駕籠を急がせ、同村の富豪下田氏方へ乗り込み、百姓側の主なる総代福田子之七氏等七、
八名を呼び出し話し合いが行われました。
先ず前橋藩の児玉氏が総代に向かって願意を述べるよう命じました。福田氏は進み出て全般に渡り
今日まであった事実を子細に述べ、農民難渋の次第を事細かに理路整然で明晰な陳述に聞き入る一同
の役人達もうなづき、前橋、岩鼻の役人はいろいろ聞きただし、福田氏は答弁をしていました。遂に
高崎藩の長坂氏は弁解に苦しみ受け身に廻り、そこで児玉、松本両氏と密談をし
「領分全体一団となって訴願するようにすれば、藩でも聞き入れるかも知れないし、同じ騒動でも罪
科も軽い、従って名主、組頭、百姓代を通してするように。」
と懇々と指示していたが福田氏は
「ごもっともで私もそう思うけれどその方法だと日数がかかり本年には間に合いません。」
と答えました。すると児玉氏は
「それでは三分の救助を行い、ともかく本年の急場を救うことにせよ。」
と言われたので余り満足はできないが願書を作り提出しました。他藩県役人が立ち会いで協定したこ
とだから高崎藩でも幾分異議もあったのですが聞き入れないわけに行きませんでした。役人は
「出願の書類には氏名を記入するようにとのこと。」
と述べました。王政維新の際でも百姓一般には姓を許されず何々村百姓誰々と称して人間の権利平等
にならなくても庶民が姓を名乗れるのは実に画期的なことでありまして、当時としては肩身の広くな
ったような感じがしたものでありました。
六十六 各総代捕らわれる
民部省へ強訴をした山田、丸茂の両氏をも辛くももらい受け入牢させ、藩でも大総代の外、続々検
挙する計画の風説が事実となり、何時どのような件で逮捕されるか分からない険悪な様相になってき
ました。
十月に入り、倉賀野下正六の堀口六左衛門氏は先年三喜蔵、喜三郎氏が護送されるときに粕沢で数
多くの農民とがれきを投げ取り返そうとしたことで捕らわれ、上正六の湯浅巳代吉もついに捕縛の不
幸に遭い鉄窓の中の人となったのは誠に気の毒なことでありました。粕沢の乱暴はこれらの人ばかり
ではないのですが岡っ引き等に顔を知られていたからのことでしょう。領内の農民は戦々恐々として
薄氷の虎の尾を踏む心地がして心穏やかではなかったでしょう。
遂にこの年の年貢も三分の救助ということになり、とにかく上納も済み、心忙しく暮れゆく年の支
払いもして迎春の準備中の二十五日というのに上佐野村の関口弥蔵、下中居村の木村主馬吉、柴崎村
の高井伊十郎氏等に高崎藩民政局より各村名主へ厳命がありました。そこで各名主も大いに驚りまし
たがやむを得ないので早速本人を呼び寄せて藩よりの命を伝え
「明日我等役人の中から誰か付き添って民政局へ出頭するから、それまでは帰宅しても良いが決して
逃げ隠れをしてはならない。」
と注意しました。
三人の総代はその夜親族や総代の者へ名主から言われたことを細かく話しました。
「明日出頭のまま留め置かれ、その上斬首の処分でも受けるような不幸に遭えばその節は家事はこの
ように頼む。」
と言うと聞き入る家人や親戚の者はこの後どうなっていくのものか憂
慮の余り涙しない者は誰一人いませんでした。殊に婦女子は声を張り
上げて泣き伏したのも無理からぬことでしょう。
明けて師走の二十六日の朝、三人の総代は各村役人一人ずつ付き添
い民政局へ出頭されました。民政局の役人は待ち構えていたという風
で直ぐ三人を白砂に呼び、取り調べをし、結局そのまま留め置きとな
り遂に仮入牢を言い渡されました。その罪状はこの春百姓多数の者の
総代となり民部省へ強訴しようとして川越町で捕らわれ高崎へ連れ戻
され放免の時減納願いをしない誓約をしたのに引き続き百姓を扇動し
たということでありました。
三人の者がこのようなわけで仮入牢を言い渡されたので各名主も驚
かれ何度か嘆願しましたが遂に聞き入れてもらえず悲しい思いで帰村しました。今日の取り調べの様
子はどうかと親族の者や組合の者は首を長くして名主の帰りを待っていたが、名主の話によれば仮入
牢を言い渡されたとのことだったので、いよいよ心痛の度が増してきました。
この出来事が領内訴願に関係のある二百数十人の総代に知れ渡るとお互いに心が穏やかでなく何時
どんなところで我が身に及ぶか憂慮していました。そんな折、今夜一夜で年が替わろうとする大晦日
の日にまたまた呼び出された人達は正観寺村の福田子之七、中尾村の小嶋掃部次、中泉村の大澤富太
郎の諸氏で皆そのまま留め置きとなり、村々には騒乱と恐怖がはいりこみ、正月を迎えるのに無邪気
な子供さえ正月気分になれず何となく沈んでいたいたというのは当然なことでしょう。
高崎藩では尚もその日呼び出しをし、下佐野村の松田作平、和田多中村の馬場安五郎、上中居村の
清水元吉、同村の清水徳次郎、同村の堤和三郎、同村の堤清右衛門、飯塚村の小平国太郎、新波村の
菊地笹太郎、楽間村の竹井馬吉の諸氏で一時にこのような多人数の呼び出しで何れもそのまま留置で
したのでなかなかの混雑でありました。
これには例の村役人が付き添って出頭しましたので、村役人が帰ってくるのを今や遅しと待ってお
りますうちに各村役人が悄然と帰ってきます。親戚や組合の者が名主の家へ押し掛けて今日の様子は
どうかと伺いいますと、名主はしばしば嘆願をしてみたが聞き入れにならず遂に入牢を言いつけられ
たとありのままを聞かせました。
一同の者は立ち返って家人にその向きを伝えると家族の悲哀はまたひとしおでした。維新の際まだ
全般に庭たる刑法というものがないから各藩で勝手に処分しなければならなかったのだから無理、の
ないことであります。
六十七 各総代の処分決定
高崎藩では予定の人達を呼びだして入牢を言い渡し、今まではただその処分についての協議ですが
今度は刑法の条項によって処分しなければならないから容易に決定しませんでした。そればかりでな
く、先に民部省からの注意もあり、また我が領内においてこのように何時までも騒動が起こるのは他
藩に対して面目もあるので日夜熱心に罪科を審議して決定しました。
今日の現行法からいえば控訴上告または弁護の道もありますが、その頃はまだ治罪法の刑事訴訟法
が発布のない時であったからこれほどの大事件でも恰も即決同様な判決を下されました。またそれを
甘んじて受けなければならなかったので、法規の不備はやむを得ないとしても人権を尊重しない裁判
は今日からして見れば到底想像のできないことでしょう。
全く農民百姓を一人の国民と考えないで犬猫のような動物として扱いにされていたので、罪状の調
べ方も圧制極まるもので、どちらかと言えば、専断即決で情状酌量などと言う暖かい血の通った判決
ではありませんでした。しかし、他藩や隣県または民部省に対しての配慮から、先の大総代のように
斬首のような決定がなかっのは不幸中の幸いと言えましょう。
今、その罪科が決定して発表されたのは明治四年一月十二日でありました。その中で倉賀野の堀口
六左衛門氏は八丈島に流罪となり、同十三年に哀れな最期を遂げたそうです。同時に捕らえられた同
村の湯浅巳代吉氏はまだ罪科の決まらない内に気の毒にも牢死されました。
そこで民部省に強訴をして藩に引き渡された丸茂元次郎、山田勝弥の両氏は首謀と見なされ両人と
も徒罪十年に処せられ、山田氏は服役中病気のためなくなりました。丸茂氏は恙なく期間満了して出
獄して、老後は悠々自適の生活を送ることはできたのは何よりのことでした。さて正観寺村の福田子
之七、中尾村の小嶋掃部次、中泉村の大澤富太郎の三氏は徒罪三年に処され上佐野村の関口弥蔵、下
中居村の木村主馬吉の両人は徒罪二年六ヶ月と決定し、柴崎村の秋山孫四郎は徒罪二年に処されまし
た。これはある方面の運動が効を奏したと当時風説があったのですが柴崎村の高井伊三郎、岡田友衛
門の両氏は幸いにも無罪を言い渡されました。上中居村の清水徳次郎氏は二年六ヶ月の徒罪でしたが
気の毒ながら牢死されました。下佐野村の松田作平、和田多中村の馬場安五郎、上中居村の清水元吉、
堤和三郎、堤清右衛門、飯塚村の小平国太郎、新波村の菊地笹太郎、楽間村の竹井馬吉の諸氏は徒罪
三年に処されました。
これが一月十二日に処分を言い渡されたのでありますが、今のように新聞はなく、検事局より犯罪
通知があるように藩より名主へ知らせがなく、あったとしてもそれは牢番の人足の請求があって初め
て知ることができるので期間については分かるものではありませんでした。そんな次第であったから
領内の者の心痛は一通りでなく留置されている総代も、大総代三人打ち首の刑に処されるのではない
か、また呼び出されていない総代達は何時我が身に累が及ぶかとろくろく眠れもしませんでした。中
には正月元旦早々我が家を忍び出て遠い他領の親戚へ年始の礼に行き、そのままそこの居候同様の身
になった者もいれば、岡っ引き等に目を付けられないように他人の家に一、二夜ずつ潜伏してこわご
わながら日を過ごした者もいたような次第でありました。
正月とはいいながら年始回りどころか、どこの家でも屠蘇のひとつも汲もうとした者もなく、無邪
気な子供までが楽しんで遊んでいる風もなく、朝を告げる鶏の声まで何となく悲哀を帯びたように聞
こえたのはその状況からして仕方のないことだったのでしょう。
老人達は涙をこぼしこんな心配をして寿命を縮めるより一層のこと減納願いをやめて、どんな粗末
な服を身につけたり食事をして、日夜稼いで年貢が納まらない状態の方がこの心痛に比べればまだ何
とか我慢できると感じていました。
諺にも泣く子と地頭には勝てない。百姓は健康でぼろを着て、朝早くから仕事をし、夜はそれぞれ
男は縄をない草鞋を作り、女は木綿糸をつむぎ、夏は草を刈って肥料を作り、冬は薪を拾い染料の木
の皮をはぎ、髪も自分で結い、是非買わねばならないのは塩だけという風にすれば年貢を納めること
ができる。自分たちが経験し祖先の言い伝え等を取り混ぜて説明やら愚痴や等を話している光景は誠
に悲惨そのままでありました。
六十八 最後の顛末
既に主導者の面々はそれぞれ処刑され、他の総代も別に調べられる様子に見えたのでこれまで潜伏
していた者も、遠方の親戚の居候となっていた者も徐々に帰宅して稼業に精を出し始めました。
訴願については新たな総代もできませんでしたが、たとえ一年限りでも減納があり、また三分の救
助等もあって、減納の素志に叶い明治二年から四年までの一大騒動も訴願の要求は完全に受け入れら
れたわけではないが部分的には確かに効果はありました。
そこでこの事件に費やした金額は百姓側の分だけとして二万五千両で当時としては実に大金であり
ました。とにかく二百数十人の総代の運営資金、一般への弁当代、宿泊代等も含まれていますから、
あながち過当ということでもないでしょう。
この年七月十四日になって太政官は各藩の名義を廃して県をおかれ、ここ上州でも高崎、安中、七
日市、小幡、吉井、前橋、沼田、伊勢崎、館林の九藩、それに岩鼻県を廃して、高崎藩をおかれまし
た。これが世に言う廃藩置県であります。このようなわけで大河内氏は藩知事を免ぜられ、ここに全
く名実ともに中央政府の太政官に属し、藩政は自然に消滅してしまいました。
太政官は従六位安岡良完氏を高崎県参事になり政務を処理され、八月太政官より一般に立ち袴、割
り羽織の着用してもよいという布告がありました。これまでの藩政の時分には名主、組頭といえども
容易に許されず、一郷一、二名特権を与えられたくらいであったのが昨年は苗字を許され、今このよ
うな布告に接したので政府が漸く人民を憐れんだ政治を取り入れてきているので、近い将来訴願した
減納についても天領同様になるということで心密かに喜ぶ者もおりました。
このように申し上げますと高崎藩とは関係がなくなってきているわけですが、まだ一部の者が時折
集合して減納訴願について協議をいている者もおりました。しかし最早主な総代はだいたい入牢して
いて残っている人の中でも随分力のある人も世の動きを見て特に活動はしていませんでした。
春も過ぎ、夏も往き、秋の十月七、八日になると一旦消えた火がまた燃え上がるように、四、五百
人の百姓があちらこちらで集合していました。石原村の観音山ではときどき気勢を上げる大きな声が
していたので高崎県庁でも聞き及んで前例もあるので放っておくことができないと県吏が観音山に出
向きました。内心期待していた百姓側は早速願書を差し出すと県吏は受け取り、
「良きに計ろう、先ず引き取れ。」
と言ったので穏やかに引き払いました。
県においてはその夜のうちに各村名主へ
「本年の分はお見取り検見に確定したから承知しておくように。」
との通達が届きました。旧来の検見のように一筆毎に坪きりするのでなく一村の作柄を上中下の三段
階に分け標準を儲け納米を定めるのでやや公平な検見だと喜びました。
そこで本事件を考えるのに最初領内上中下東西の五郷六十一か村より起こり、一カ年にしても願が
聞きいれられ、三分の救助を得た年もありましたが、そのために斬首の刑に処された者三人、流刑が
一人、牢死した者が三人、二年以上の徒罪に処された者十数人でこの人々は悉く上中下の郷の人で、
東西の郷の人はいないので奇妙に思いました。またまた二万幾千両の金も大概上中下の三郷の支出で
した。それに引き替え減納や救助は領内一帯でした。これが当時の状況を研究しますとその疑いが晴
れるのであります。
当時藩士以外で藩主に親しかった人はいましたが、石原村清水寺の田村仙岳、南大類村観音の別当
小園江丹宮の両氏ほど信望があり、親密にしていた者はいませんでした。ですから藩の重要事件には
いつも諮問に預かり減納訴願についても初めより諮問がありました。その一人の小園江丹宮師で、師
の祖は水戸の藩士で修行して大僧都までいった人で南大類村では観音の別当となって近郷の子供達を
集めて経書などを研鑽したりして教育に意を尽くされ、師に教えを乞うた者は数百人とも言われ羽鳥
権平、久保田房次郎両氏もその一人でありました。そこで減納訴願の率先者で年も若く二十二才、二
十五才で身を捨てて難に赴いた羽鳥、久保田の両氏が一大事件を引き起こすに当たり小園江師に相談
しないわけはありません。東山道鎮無総督の宮より出された布告により従来の苛政を是正しなければ
ならないと家老とも議論したそうであるし、農民が枡方に押し寄せたときも諮問に応じ大激論を交わ
したそうである。このとき師は
「日本広しといえども高崎藩ほど税の高いところはない。かの七合三勺の摺り立ては比類ない苛酷の
方であるから願を入れてくれ。」
と反対者が多い中で勇敢にもそう述べました。なおも
「世の大勢を見ると近い将来必ず一大変革があるだろう。今百姓の減納の哀願を入れなければ為政者
の取るべき道ではない。」
と誠意をもって諫言したので列席の者も納得し代官金田氏を太政官に派遣したということであります。
減納も一年だけとして決定し、その後は強いて訴願する者はどしどし捕まえて入牢させるいう重役
が意向がよく分かったので羽鳥、久保田両氏と総代天田勇造氏に
「強いて訴願し辱めを受けぬよう、ここしばらくは謹慎し、どうしと申し合わせ勤倹の方法を設けた
らどうか。」
と進言したそうであります。このように勤倹を進言したのは師ばかりでなく田村師も大いに賛成され
て石原村、乗附村の有志に進言をしたそうであります。両氏は当事件について藩と百姓の中に入って、
藩の対面を傷つけないよう、百姓側の考えも理解するよう、できるだけ罪人を作らないようにと骨折
ったことは分かるでしょう。しかし、両氏は異なるところもあり、田村師はやや藩よりで四民六藩と
言われ、小園江師は百姓よりで六民四藩と言われていました。
とにかく東郷に小園江師あり、西郷に田村師あって円満な労を執ったので東、西郷からほとんど罪
人を出さずにすんだのであります。この東西郷の中でも捕らわれるべき人は十人近くもいました。中
でも羽鳥、久保田両氏、石原村の桜井勘六氏は田村師と別懇であるので本事件につき初めから田村師
と小園江師との間を奔走し羽鳥氏とも密会しこの一大事件を引き起こしたのでした。
小園江師は羽鳥、久保田の両氏が受難されそうになったので両氏を別懇の林大学頭の家老に頼んで
ひそかにそこへ潜んだそうであります。また田村師も桜井、江積氏の両人のため一時姿を隠したので
難を免れられたとのことです。羽鳥、久保田は東京で町家住まいをして民部省へ出頭したということ
であります。以上お話したことを総合玩味していただけると東西両郷から罪人が一人もなかったこと
が分かると思います。
本事件は竜頭蛇尾に終わり政治変遷の結果、露骨に言えば相手のない相撲は取れない形で終わった
感じがします。この高崎支配所減納訴願事件、即ち五万石騒動は領内百姓の生活が難渋を深めてきて
いるので、年貢を他領並にしてほしいと領内六十一ヶ村がおよそ二年間に渡り、大総代を中心に組織
的、計画的、継続的に訴願運動をしたものであります。その間、幾多の犠牲者を出し、莫大の費用を
かけ、多くの辛惨労苦を甘受しましたが運動が終わる時点では願いが完全に叶ったわけでありません
でした。しかし、一年限りの減納や救助という形で効果を現しました。また、地租改正等農民に対す
る施策上多大な影響を及ぼしたのでこの訴願運動は成功したといってよいでしょう。
この後、日本国中、法規の元で人民に土地を平等に分け、地価をその土地の資質に合わせ、収入を
考慮し、極めて公平に徴税方法を採った政治ぶりは民意に適合した処置といわなければなりません。
以上私は自己の信ずることだけを申しました。本事件は多年関係者の頭の中に深く印象づけられた
ことですが記憶の失するところもあると思います。後日、詳しく考証して誤り等を訂正したいと思っ
ておりますが、そのとき充分な補遺をいたす考えでおります。
五万石騒動 了
《資料集》
一 難語句等の意味 ( )はページ 小学館刊「国語大辞典」等による
延米(20) 代金の支払いを後日にのばす約束で買い込んでおく米。利息などを見込むと
時価より高くなるが、これを転売して急場の入費に充てるために行われた。
口米(20) 年貢高に応じて一定の比率で徴収する米
根取り(20) 年貢収納の標準に用いた一反あたりの基準米
一瀉千里(36) 一度流れ出すと千里も走るような勢い
育亀の浮木(45) 大海原に浮いている木、その木の孔に目の見えない亀があうこと、確率の低
いことをたとえて言う。
幣束(56) 幣串にはさんだもの、神前の供え物 ^
驚天動地(57) 世間をひどく驚かすこと
町奉行(58) 市中の行政、司法を司るところ
永取り(63) 金銭で納める徴税
岡っ引き(87) 町奉行所の同心に私的に抱えられ犯罪人の探索や逮捕に当たった者、
大目付(97) 老中支配に属し、藩政等の監察にあたった
怒髪天をつく(102)怒りのため髪が天をつく、激しい怒りの有様
抱腹絶倒(102) 腹を抱えて大いに笑うこと
懐柔的策略(111) 巧みにてな付けること
高割り(132) 持ち高に応じて割り付けること
中座(161) 囚人の縄取りを勤めた者
朝令暮改(164) 命令が度々変わってあてにならないこと
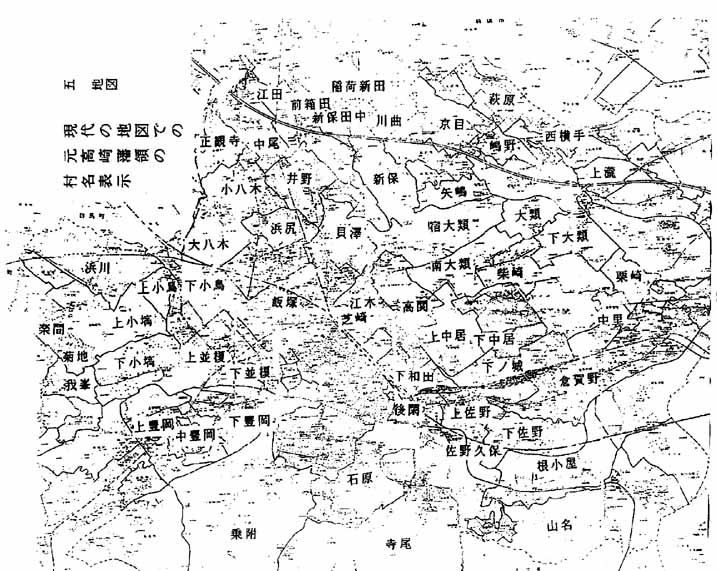
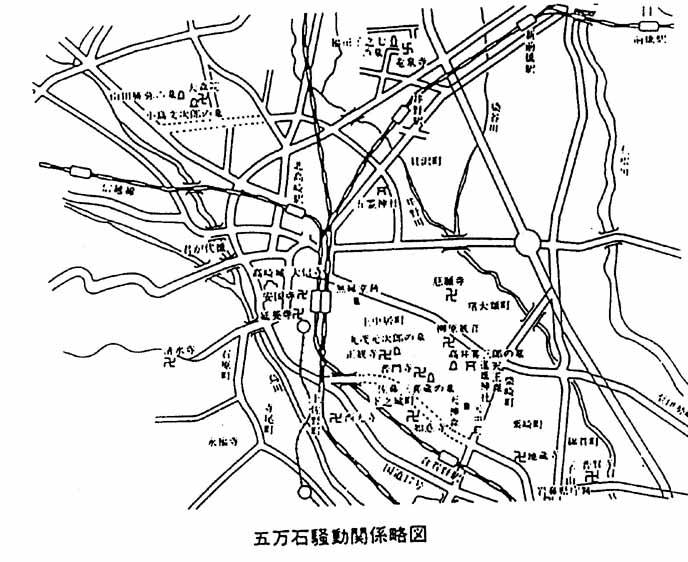
訳者あとがき
一 この訳本の制作について
この「五万石騒動」の現代語訳を始めてから二ヶ月経ち、ようやくあとがきを書くまでにこぎ着け
ました。「何もそんなにあわてなくてもじっくり時間をかけて良いものを作ったらどうか。」という声
が聞こえそうでありますが、どちらからいうとのんびりと時間をかけてやるより、多少無理をしても
集中的にやる方が向いているし、五万石騒動の話をこよなく愛した兄の一周忌に間に合わせようとい
うことで、かなり身体的にも精神的にも自分を追いつめてこの現代語訳を完成させました。
この現代語訳の目的の一つは誰にでも分かるような内容を目指しているので、短期間でも文章も練
りに練らなければなりません。しかし、これはなかなか難しいことなので、今の若い人たちにおよそ
理解できるところまでいけば、それで第一版を発刊し、それからじっくり版を重ねて、良いものに仕
上げて行く方が私には合っていると思ってこの方法を選びました。
二 五万石騒動についての評価
文献等により本事件を分析したいと思います。
まず、本書の三十一の高井喜三郎の友人の発言を抜き出してみたいと思います。
「自分は不学短才で世事の状況も闇く今貴殿の御説を受け給感心はせしも熟 々前途を推考するに王政
復古の第一階段を登りしまでの事、今二三年も経過せば世間も静り御仁政も晋く往ま亘り、矯正仁慈
の御政事に為らば何にも左様に危険を冒してまでも減納を願はずとも自然減免の御徳に浴することを
得らるるものと愚考する」
次に本書の六十七の老人達の声(騒動関係者がぞくぞく逮捕されているとき)を聞いてみると、
「こんな心配して心配して寿命を縮むよりいっそ減納願ひなど中止て貰ひたいかに粗服や粗食を為し
夜に日継ひで稼がねば御年貢が納まらないとした処が此の心痛には替へられない」
利根川靖幸氏は「たかさきの夜明け前 高崎五万石騒動」の中で次のように述べています。
「幕末から明治初年の頃、田の年貢は一般に五公五民か、六公四民であった。五公五民とは収穫が十
俵あった場合に、五俵は年貢として領主に納め、残る五俵を農民が取得するのである。高崎藩におい
ては表向きは五公五民でであったけれど、実際の取り立ては八公二民位であったという そのために
種々のからくりが行われた。例えば、籾の摺り立て計算において、籾一升につき玄米五合というのが
一般であったが、高崎藩においては七合三勺でるものとして計算した。また、納米一俵は四斗二升と
定められていたが実際には、四斗三升六合二勺く入れることを慣例とした。その他、畑・居屋敷の米
納、年貢米納入時における米見役等への饗応等、まことに苛酷な取り立てであり、農民の負担は極限
に達した。泣くこと地頭には勝てないと言うが、当時の農民は、自分で作った米も思うように食べら
れず、襤褸を着て、早朝から夜遅くまで働き、どん底の生活に呻吟していた。従って、五万石領下の
農民の騒動に立ち上がるのは、やむを得ないことであった。農民は総立ちになって叫んだのである。
年貢の取り立てを、岩鼻県や新領と同じ程度 に軽減してほしい・・・、と」
最後に萩原進氏は「群馬県人」の中で次のように述べています。
「群馬県人の、あまりに人を疑わない愚直の最もいい例が、明治維新の夜明け発生した悲惨な五万石
騒動である。」
「結局大総代三名を処罰することになり、佐藤三喜蔵、高井喜三郎の両名を明治三年二月に断罪に処
し小島文次郎もまた断罪に処された。もちろん、藩では新政府に対して伺いを出して許可されてやっ
たことであるが、政権を握った新政府の幹部が、新時代に処するのに自身が泣く、人気取りの布告を
出し、それをまともに信じた高崎藩五万石領農民の主張を罪ある者として処断したという事は、少な
くても現代においては許されるべき者でない暗黒政治の一断面といえよう。新政府のずるい本心を見
抜くことができず、愚直にこれを信じた群馬県民の悲劇の一つである。為政者の欺瞞に踊らされた例
は他にも見られ、内村鑑三が上州人は馬鹿正直だと言ったことを歴史的に物語るといえよう。」
以上五万石騒動に対する考え方は多種多様であります。この騒動には総代の運営資金、一般への弁
当代、宿泊代等で二万五千両の巨額の経費がかけ、農民達は稼業を離れ多くの身体的にも精神的にも
犠牲を払い集会等に参加しましたが、結果的には一年間の減納と一年間の三分の救助しか得られず、
反面三名が斬首の刑に処され、二十人近くが二年以上の徒罪に処されしまいました。労力の割には得
るところが少なく、失った面が大きな気もします。また、百姓の老人達が言うように騒動などを起こ
さずに泣く子と地頭には勝てぬ的で重税に甘んじて堪え忍びつつましく生きた方が余計な神経を使わ
なかったもしれませんし、喜三郎氏の友人のように二、三年待てば税法も変わり、暮らしも楽になっ
たかもしれませんし、萩原氏の言うように群馬県人の人を疑わない人の良さが出たかもしれません。
しかし、この騒動には一般の農民一揆には見られない特色があります。一般の騒動は未組織農民によ
る自然発生的な行動でありましたたが、この騒動は事前の打ち合わせを何回となくやり、五十カ村の
多くの農民が参加し、大総代の統率力により 暴動や不謹慎なことはせず、減納のため正々堂々と行動
したのである。また、一般の騒動だと線香花火のように瞬く間に消えてしまうのにこの騒動は計画的
に継続的に行われました。
苦しい重税や役人達の農民に対する軽蔑的態度に甘んじることなく多くの農民が団結し、力を合わ
せ一つの目的に徹することができたのは結果よりもその行為自体すばらしいことであると思います。
また大総代は寝る間もないほど東奔西走したり、話し合いを続けたりして、農民のために命を投げ出
した義民的行為、農民達の協力的で労力を惜しまず提供した行為に対して、総代や農民の子孫達や群
馬県人はもっともっとこのことを誇りに思ってもいいと思うのであります。
三 細野格城著「五万石騒動」について
この本は実際著者が十五才の時騒動に参加し騒動の一部を体験しており、「桜宗五郎」や「磔茂左
衛門」などは伝承の部分が多いので、史実的にはそれより正確度はかなり高いはずです。また、格城
氏は実際騒動に農民側として参加していながら、実にこの騒動を冷静に受け止め、ときには農民の心
情を、ときには役人の心情を捉え、第三者的にこの騒動を捉えています。格城氏は全部自分の目を通
したわけではありませんが、実際その場面を見た人等から実に細かく聞き取っています。
総代の集まりに参加した達の名前とか、炊き出しのとき、炊き出しを戴いた村名や人数、正米を戴い
て自炊した村名や人数、集会の時の焚き火の数とか細かに調べその精力的努力に対して全く頭が下が
ります。
文章の構成も史実的にだけ捉えるのでなく、炊き出しにおける町民の農民に対する思いやり、集会
の時見ず知らずの人に宿を貸す人たちの優しさをクローズアップしたりしています。素っ裸で奔走し
た若者の話とか、田村仙学僧の話などエピソード的なものも取り入れ、それが却って史実的な正確度
を深めたり、物語要素を深め読者を魅了させてしまうと思うのです。この本を読むと五万石騒動の史
実だけでなく当時の人の生活の様子や、忍耐強さ、協調性、心優しさなどを感じ捉えていて、この頃
は貧しくて苦しい時代でありましたが人間の暖かさがあって良かったと、この事件の百三十年後物質
的には格段恵まれているが自己的に生きている人が多い中、つくづくそう思うのであります。
文章は私たちから見れば、ことわざや難語句が多かったり、一つの文が長かったりして分かりづら
いところもありますが、同じ意味する言葉もその状況に合う言葉にして、その場の様子を的確に表現
しています。私はこの本は史実的にもすばらしいですが、文学的にも優れていると思うのです。
四 最後に
佐藤家初め、この騒動に関係した子孫の方々、この騒動に関心のある方々、ぜひこの現代訳本や
原書等によりこの「高崎五万石騒動」を子孫等に伝え、先祖の偉業を讃えて欲しいのです。そして、
先祖がこの偉業を成し遂げ、命を惜しむことなく全精力を費やし、多くの人たちに尽くしたことに対
して、もっと誇りと自信を持って欲しいのです。
この本を製作にするあたり、従兄の佐藤信弥氏等多くの方から、貴重な資料を提供して戴きました。
ほんとうにありがとうございました。
この現代訳本は浅学の者が短期間で仕上げたものでありますから、訳も不正確な部分も多いと思い
ます。お気づきの点がありましたら是非訳者までご一報ください 。心よりお願い申しあげます。
TOP INDEX