 カニ太は星を見るのが好きでした。その夜も、そろそろと岩場によじ登ると両手を広げるようにして夜空を見上げておりました。天頂近くにはカニ太の大好きなプレアデス星団が輝いていました。 カニ太は星を見るのが好きでした。その夜も、そろそろと岩場によじ登ると両手を広げるようにして夜空を見上げておりました。天頂近くにはカニ太の大好きなプレアデス星団が輝いていました。宇宙はどうなっているんだろう。カニ太は星を眺めながらブラックホールのことを考えたり、宇宙のはじまりのことを考えたりするのがたまらなく好きでした。なんだか星を見ていると、不思議とその答えがわかりそうな気がするのです。あたり一面、川の音が響き渡っていました。 カニ太は冷え切ったハサミをこすり合わせながら岩場から降りてきました。口か  らぶくぶくと小さな泡を出して、まるで独り言でも言っているかのように静かに小川の中に戻って行きました。 らぶくぶくと小さな泡を出して、まるで独り言でも言っているかのように静かに小川の中に戻って行きました。浅瀬の中は真っ暗でしたが、地上よりはすこしばかりぬくぬくしていて、ホッと気持ちが落ち着くような気がしました。カニ太は川の流れに逆らって進みました。そして、今にも流れに押し戻されるようになりながら、やっとの思いで、大きな岩の所にたどり着きました。その岩陰に、カニ太は大事な青い小石をいつも隠しておいたのです。 そっと岩陰にハサミを忍び込ませて、カニ太はびっくりしてしまいました。どういうわけかいつもきちんと置いてある場所に小石がみつからないのです。右のハサミ  で探っても左のハサミで探ってもみつかりません。 で探っても左のハサミで探ってもみつかりません。「ああ、どうしよう。大変だ。」あの青空のように青く澄んだ小石がないと大変なことになってしまうのです。カニ太は狂ったように岩の回りをあちらに行ったりこちらに行ったりして、それはもう必死で小石を探しました。 ちょうどその時、先程まで雲間に隠れていたお月様が姿を現しました。浅瀬の中が少し明るくなりました。目を凝らしてよーく見ると、  大事な小石を隠しておいた岩から少し離れた川上に、ぼんやりと青く透き通った米粒ほどの小さな小石が輝いているのが見えました。流れに逆らいながら、大急ぎで、カニ太は小石の所までたどり着きました。 大事な小石を隠しておいた岩から少し離れた川上に、ぼんやりと青く透き通った米粒ほどの小さな小石が輝いているのが見えました。流れに逆らいながら、大急ぎで、カニ太は小石の所までたどり着きました。「ああ、よかった。こんな所にあった。」ほっとする間もなく、カニ太は息を殺してじっとあたりの様子を伺いました。おかしいのです。川下にあるのでしたら、小石は川の流れに流されたのかもしれないのですが、小石は勘違いでも何でもなく、確かに川上に移っていたのです。「誰だ、誰が僕の青い小石を動かしたんだ。」 実は、カニ太の仲間は誰もが例外なく、この秘密の青い小石をハサミの間にはさんで持っていました。地球広しと言えど、こんな蟹はカニ太の仲間を除いて他に見たことがありません。 それにカニ太の仲間には、おかしな特徴がありました。ちょっと信じられないかもしれま  せんが、気分がよい時には彼らの鼻は普通のまま、何の問題もありません。しかし、気分が悪くなると、つまり、怒ったり悲しんだりすると、手で押さえようが何をしようがどうしようもなく、鼻がスルスルと伸びていってしまうのです。 せんが、気分がよい時には彼らの鼻は普通のまま、何の問題もありません。しかし、気分が悪くなると、つまり、怒ったり悲しんだりすると、手で押さえようが何をしようがどうしようもなく、鼻がスルスルと伸びていってしまうのです。
それが、です。不思議なことに、この青い小石をハサミにはさんでいると、余程の激しい怒りや悲しみでもない限り、鼻は普通のままでいられるのです。一人で部屋に居るときを別にして、仲間と会うときにはいつもみんなこの青い小石をハサミにはさんでいました。それがないと社会生活ができない必需品、人間で言えば洋服のようなものであったのです。 「ああ、どうしよう。どうしたらいいんだ。」なんとか小石は見つかったもののカニ太の気持ちはおさまりません。それもそのはずです。この小石にはもうひとつ大事な秘密が隠されていたのです。 それをここに述べることは簡単です。しかし、その前にひとこと言っておかなければならないことがあります。この大事な秘密は決してこれを他の人に言ってはならないのです。もしも万一、この秘密を他の人に言ってしまうようなことがあると、大変です。言ってしまったその瞬間に、言ってしまったその人の鼻がカニ太の仲間と同じように、気分次第で伸びたり縮んだりしてしまうことになってしまうのです。私はそういう人を何人か見たことがあります。くれぐれも、「ここだけの話だけなんだけれどさあ。」とかなんとか言いながら、誘惑に負けて、この秘密を他の人にしゃべってしまうことのないよう気をつけてください。 その大事な秘密は、青い小石にありました。青い小石の中には、それを 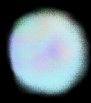 持っていた人のぐっと鎮められた気分がひとつ残らず詰め込められていたのです。青い小石を指と指の間にはさんでよーく観察するとその鎮められた気分のひとつひとつが実にリアルに見えてきます。私は見たことがないので本当の所は分かりませんが、それはまるで八ミリビデオを見てでもいるかのようにはっきり見えるということなのです。 持っていた人のぐっと鎮められた気分がひとつ残らず詰め込められていたのです。青い小石を指と指の間にはさんでよーく観察するとその鎮められた気分のひとつひとつが実にリアルに見えてきます。私は見たことがないので本当の所は分かりませんが、それはまるで八ミリビデオを見てでもいるかのようにはっきり見えるということなのです。あくまでも例えばの話ですけれど、「へえ、そうなんだ。みんなの前で犬の糞を踏んでしまってみんなから馬鹿にされたとき、カニ太の奴、まるで平気そうな顔をしていたけれど、本当はかなり動揺していて、今にも泣き出しそうだったんだ。結構、カニ太は弱虫なんだなあ。」とか、まあそんな具合にわかってしまうわけなのです。 ですから、カニ太の仲間の間では自分の小石以外の小石を持つことは、絶対にやっていけないこと、タブーとして固く固く禁止されていました。実際、彼らの法律には、肉体的殺人罪の条文と並んで精神的殺人罪の条文が記されていたほどです。もちろん、その立証は確かにかなり難しいことではありました。 「誰かがきまりを破って僕の秘密を覗いたんだ。そうとしか考えられない。」その時、カニ太の鼻は恥ずかしさと激しい怒りから、それはそれは異常に長く伸びておりました。 今にも泣き出しそうになりながらカニ太は、浅瀬にじっとしておりました。これからどうしていいものか、皆目検討がつきませんでした。ちょうどその時です。岩陰で何かが動く気配がしました。カニ太は、ハッと我に返り、緊張した面持ちで身体を硬くしてあたりの様子を伺っていました。 岩陰から姿を見せたのはなんとカニ太のお母さんでした。その姿を見たとたん、もうどうしようもありませんでした。カニ太はお母さんが犯人だと、そう、勝手に思い込  んでしまいました。私は知っていましたが、実際はそうではありませんでした。カニ太の青い小石をそっと覗いてしまったのはカニ太の1歳年上の姉でした。姉は日々成長し、一体何を考えているのか分からないカニ太の心の中が知りたくて、そっとカニ太の小石を手にとり、カニ太の心の中を覗いてしまったのです。 んでしまいました。私は知っていましたが、実際はそうではありませんでした。カニ太の青い小石をそっと覗いてしまったのはカニ太の1歳年上の姉でした。姉は日々成長し、一体何を考えているのか分からないカニ太の心の中が知りたくて、そっとカニ太の小石を手にとり、カニ太の心の中を覗いてしまったのです。「お母さんなんか大嫌いだ。お母さんなんか、早く死んじまえばいいんだ。」カニ太は長く伸びた鼻を引きずるように叫びました。お母さんは、何のことか、さっぱりわからず、おろおろと、自分の脇をすり抜けるように走り去っていくカニ太の様子をただ呆然と眺めているだけでした。 泣きながら、身体を引きずるようにカニ太は、再び岩場の上に登っていきました。もう川の中には戻りたくない、母親の顔なんかもう二度と見たくない、そんな気持ちでいっぱいでした。 泣き叫びながら、カニ太には、気持ちの上でちょっとひっかかるところがありました。お母さんの脇を風のように通り過ぎたそのとき、お母さんの鼻がカニ太の鼻よりももっと激しく、しゅるしゅるしゅると異様な勢いで長く伸びていったのをカニ太は見逃してはいませんでした。それから、お母さんの右の手の大きなハサミに、白い包帯のようなものが巻かれているのも見えました。「あれ!お母さん、どうしたんだろう。」走り去る瞬間、カニ太はそう思いました。しかし、一度口から出た言葉は、もう自分でもどうしようもありません。元には戻らないのです。 「ふん、どうせ大したことじゃない。ああ、そんなことよりも、お母さんは僕の青い小石を僕に内緒でそっと見たんだ。少しぐらい怪我をしたって、それは自業自得。心配してやるほどのことじゃない。」カニ太は自分に言い聞かせました。 岩場の上に登り、涙に曇る目で星を眺めていましたが、しかし、カニ太の目に  は星はひとつも見えていませんでした。それというのも、お母さんの鼻が長く伸びるところを、カニ太は生まれて初めてその時見てしまったからです。それに、やっぱり、カニ太はお母さんの右手の白い包帯のことが気になって仕方がなかったのです。 は星はひとつも見えていませんでした。それというのも、お母さんの鼻が長く伸びるところを、カニ太は生まれて初めてその時見てしまったからです。それに、やっぱり、カニ太はお母さんの右手の白い包帯のことが気になって仕方がなかったのです。「お母さんが悪いんだ。何で僕の青い小石を拾って見たりしたんだ。ああ、考えれば考えるほど許せない。バチがあたったんだ。人の秘密を覗いた罰なんだ。」カニ太はそうつぶやいて、乾いた笑い声を上げました。しかし、その笑い声は夜空に響き渡る川の音に、一瞬のうちに打ち消しされてしまいました。星は何もなかったかのように、美しく輝いておりました。 どの位時間がたったのでしょうか。鼻が他人の目にはほとんど分からないくらい短かくなってから、カニ太は家の中に戻ることにしました。深い悲しみに、心はひどく疲れていました。早くベットにもぐって、すぐにでも眠りたい気持ちでいっぱいでした。 家の扉を開けて、そーと中に入ろうとした時、カニ太は家の中からお父さんの声が聞こえてくるのを耳にしました。どうやら、お父さんが会社から帰ってきたようです。 「まあ、不幸中の幸いさ。あんな大きな石が落ちてきて、右手のハサミを潰しただけで済んだんだから。へたをすれば命も危なかったところだよ。いつまでも、そうメソメソするもんじゃあない。」居間の扉から覗いてみると、お父さんはネクタイをはずして、靴下を脱いでいるところでした。 「しばらく傷口はずきずき痛むかもしれないけれど、まあ、仕方ない。本当に不幸中の幸いなんだからなあ。医者も言ってたじゃあないか。明日にでもなれば、腫れもだいぶ引いてくるって。俺もできるだけ早く会社から帰ってきて、家事の手伝いでも何でもやるからさ。まあ、お母さん。そう、沈み込まないで、頑張ってくれよ。」  カニ太の目にはお母さんの俯いた顔がぼんやり見えました。俯いた顔の下の鼻はまだ伸びたままです。伸びた鼻の下からは、涙がこぼれ落ちていました。 カニ太の目にはお母さんの俯いた顔がぼんやり見えました。俯いた顔の下の鼻はまだ伸びたままです。伸びた鼻の下からは、涙がこぼれ落ちていました。カニ太には母親のハサミの傷の痛みも心の傷の痛みも、みんな自分のことのようによーく分かりました。 (ああ、あの時お母さんは、大事なハサミを潰して悲しくて仕方なかったんだ。それなのに僕は、お母さんに何てことを言ってしまったんだ。死んじまえ、だなんて。ああ、きっと、あの時、お母さんは病院から帰ってきたところだったんだ。それを、僕は勘違いして。お母さんは僕の小石を盗み見なんかしていない。お母さんは、そんなことをする人じゃあないんだ。お母さん、ごめんなさい。)カニ太は我を忘れて居間の扉を開けると、俯いていた母親の胸の中に飛び込んでいきました。 「お母さん、ごめんなさい。」母親は、カニ太のうめくような泣き声に全身で応えました。「いいのよ。カニ太。いいのよ。カニ太。」 月がこうこうと照っていました。浅瀬の音が星空まで届きそうな夜でした。父親にはカニ太の涙の本当の意味が分かっていませんでした。 夜もだいぶ更けているというのに、カニ太の姉だけはまだその時、家に戻っていませんでした。 |